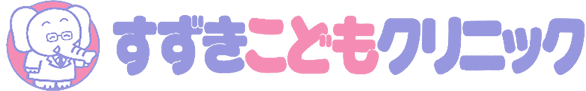小児科疾患・アレルギー疾患全般に対応

新生児から思春期までのお子様の免疫システムは、大人とは異なります。また、お子様は自覚症状を伝えることが難しい場合もあります。当院ではそんなお子様の体調不良に対して、丁寧な診察と適切な治療を心がけております。症状に合わせて検査や処置を行い、その原因や治療法についてわかりやすく説明させていただきます。また、お子様の成長や発達に関しても、お気軽にご相談ください。
さらに当院では、発熱や下痢、咳、鼻水といった一般的な小児科の疾患以外に、皮膚感染症(とびひや水ぼうそうなど)、アレルギー疾患(アトピー性皮膚炎、食物アレルギー、喘息、アレルギー性鼻炎など)も診療しております。予防接種や健康診断といった予防医療にも力を入れておりますので、体調が悪い時だけでなくお子様の健康に関して何か気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。
当院での診察や検査の結果、より詳細な検査や入院が必要となるケースでは、連携した地域の病院へご紹介いたします。また、外科や耳鼻咽喉科、眼科といった他の専門領域にまたがる疾患が見つかった場合も、それぞれの専門医をご紹介いたします。
お子様によくある症状
発熱

子どもの発熱の原因の多くは感染症によるものです。一般的には37.5度以上を発熱と考えます。感染症を引き起こすウイルスは熱に弱いことが多いため、体は高熱を出すことでウイルスと戦っています。つまり、発熱は体の中で起こる免疫の反応であり、熱を急いで下げる必要はありません。ほとんどの場合、発熱は2~3日が続いた後、自然に下がっていきます。一方で、発熱により水分摂取や睡眠の確保が困難な場合は解熱剤を使用した方が良いでしょう。
生後3ヶ月未満の発熱の場合は、髄膜炎等の重症な感染症である可能性も考えられるため、速やかにご受診ください。また、川崎病などの自己免疫疾患や腫瘍などが発熱の原因となっている場合もあります。
受診が必要な目安
- 食事や水分を十分に摂取できていない
- おしっこの回数が少ない
- 機嫌が悪い
- 顔色が悪く、元気がなく、ぐったりしている
- 呼びかけても反応が弱い
- 頭やおなかなど、からだのどこかを強く痛がる
- けいれんを起こした
- 生後3ヶ月未満
など
上記以外でも、3日以上発熱が持続する場合や、普段と「何か違う」様子が見受けられる場合は早めに受診をしてください。
発熱時のケア
温度調節について
熱が出たばかりの時は寒気が出てくることが多いので、布団や衣類を調整して体を温めるようにしましょう。その後、手足が熱く、顔が赤くなってきた場合は、衣類を調整して薄着にしたり、首や脇の下、足の付け根といった太い血管が通っている部位を冷やしたりしても良いでしょう。ただし、お子様が嫌がる場合は無理に冷やす必要はありません。
なお、3ヶ月未満のお子様では、体を冷やすと体温が下がりすぎてしまうため注意が必要です。
解熱剤の使用について
解熱剤は一時的に(約4~5時間程度)熱を下げるだけで、病気を治す効果のある薬ではありません。熱のせいで睡眠や水分摂取ができないような場合には解熱剤を使用しますが、たとえ熱が高くても元気であれば、使用する必要はありません。
なお、生後6ヶ月未満のお子様には、原則解熱剤は使用しません。
食事について
熱がある時や体調が悪い時、食事はできるだけ消化の良いものを食べるようにしましょう。食欲がない場合、無理に食べる必要はありませんが、脱水症状や低血糖を防ぐために水分や塩分、糖分はとるように心がけてください。
入浴について
熱があっても、元気があれば入浴は可能です。その際はぬるめのお湯で、短時間だけの入浴にしましょう。
※新型コロナウイルス感染が疑われる場合は事前にご連絡をお願いいたします。
(例:ご家族が新型コロナウイルスに感染しているなどの濃厚接触がある、味覚障害などの特有な症状があるなど)
また、ご来院いただく方全員の体温を確認させていただいております。
ご来院前に体温測定をお願いいたします。体温が不明な方は非接触型体温計で体温測定をさせていただきます。
37.5℃以上の方は発熱患者様と同じ第2待合室でお待ちいただきます。
なお、ご入館は原則として患者様と保護者の方1名のみとさせていただいております。
咳
咳は身体を守ろうとする反応であり、空気の通り道である気道から異物や痰などの粘液などを排除します。特に子どもでは風邪の症状の1つとして現れることが多いですが、一口に咳と言っても、痰が絡むものや乾いたもの、ゼーゼーするなど、多くの種類があります。
風邪の咳は3週間程度で改善することが多いですが、悪化はないものの咳が長引く感染後咳嗽という病態があります。
診断を行う際は、咳がどの程度の頻度で起こっているか、どのくらい続いているか、どんな種類(乾いた咳、痰が絡んだような咳、オットセイの声のような咳など)か、胸の音はどうなのか(ゼーゼー・ヒューヒューしているのかなど)などを確認します。
咳の原因の多くは、風邪などの呼吸器感染症です。症状が強い場合は気管支炎や肺炎になっていることも考えられますので早めに受診をして下さい。そのほかにも、咳が長引いているときは気管支喘息や副鼻腔炎なども原因として考えられます。突然の咳の場合には気道異物やアレルギーが原因になっていることもあります。
受診が必要な目安
- 呼吸の度にゼーゼー・ヒューヒュー音がする(喘鳴)
- 息を吸うときにのどの下、鎖骨の上や肋骨の下がくぼむ(陥没呼吸)
- 肩で呼吸している、苦しそう
- 咳き込んで眠れない
- 顔色が悪い
など
咳の原因になる主な疾患
かぜ(急性上気道炎)
かぜの多く(8〜9割)はウイルス(ライノウイルス、コクサッキーウイルス、RSウイルスなど)の感染により引き起こされ、のどや鼻といった上気道に炎症が起き、咳、鼻水、発熱、のどの痛み、頭痛などの症状が出ます。5歳未満のお子さんは年に6〜12回かかるといわれています。多くは10日前後で症状は改善しますが、咳が3〜4週間長引くことがあります。治療は対症療法が基本であり、去痰薬や解熱剤などを処方しますが、水分や栄養の補給や十分な安静が大切です。症状が長引く場合は、中耳炎や肺炎などの合併も考えられます。
急性気管支炎・肺炎
かぜは上気道(鼻やのど)の炎症ですが、その炎症が気管支や肺まで広がると気管支炎や肺炎になります。聴診である程度診断可能ですが、マイコプラズマ感染症など聴診所見に乏しい場合もあります。症状や経過に応じて抗菌薬治療が必要な場合もあります。呼吸状態や経口摂取状態が悪い場合には入院治療が必要なことがあります。
- クループ症候群(急性喉頭気管気管支炎)
- 副鼻腔炎(ちくのう症)
- 気管支喘息
- 心因性咳嗽
心理的な要因によって長引く咳の事です。気管支炎や肺炎、副鼻腔炎、喘息など咳の原因となるその他の病気が無いことを確認していくことで診断をすすめていきます。日中覚醒しているときに乾いた咳を繰り返し、咳払いのような咳も多いです。眠っているときや何かに集中しているときは咳が少ないことも特徴の一つです。心理的な要因がはっきりし、それに対応していくことが治療になります。咳が長引く際はご相談ください。
鼻水
お子様の鼻水の原因は大きく2つに分けられます。
そのうちの1つは風邪です。お子様は免疫機能が十分発達していないため、ウイルスや細菌への感染が起こりやすくなっています。つまり大人より風邪を引きやすく、鼻水も出やすいということになります。
もう1つはアレルギーです。近年、アレルギー性鼻炎はお子様でも発症しやすくなっており、花粉やダニなどによるアレルギー性鼻炎も、お子様の鼻水の原因になります。
のどの痛み
のどの痛みは、乾燥やのどの使いすぎといった様々な原因によって引き起こされますが、主な原因は感染症です。風邪やインフルエンザ、ヘルパンギーナ、手足口病、溶連菌感染症、アデノウイルス感染症といった感染症によってのどの痛みが生じます。
嘔吐
子どもの場合、多くはウイルス性胃腸炎が原因です。しかし、腫瘍や髄膜炎、消化管閉鎖、腸重積などの重篤な疾患がかくれている場合もあり、年齢によってみられる疾患は異なります。
頻回の嘔吐や症状が長く続く場合、また経口摂取が困難、保護者が「おかしい」と感じたときはすぐに受診してください。
下痢
下痢は、柔らかい便や水状の便が頻繁に排泄されるというのが特徴です。母乳やミルクを飲む時期であれば、柔らかい便が出ても多くの場合、問題ありません。ただし、普段よりも排便の回数が増えたり、水様便になったりした際は注意が必要です。下痢の原因の多くは感染性胃腸炎ですが、症状が長引く場合は乳糖不耐症を発症していることが多いです。
便秘
便秘は何らかの原因によって排便回数や便の量が減たり、また排便時におしりの痛みで泣いたりうまく排便できない状態です。便秘を起こしやすい時期や契機は、母乳からミルクへの移行や離乳食の開始(乳児期)、トイレトレーニング期(幼児期)、通学の開始や学校での排便の回避(学童期)などが知られています。うんちが貯まることで徐々に排便時に痛みを伴うようになり、うんちを我慢するようになります。するとさらにうんちが貯まり、うんちの出口近くの直腸が拡張し伸ばされ、便意の感覚がにぶくなり、ますますうんちがたまってしまう「悪循環」が起こります。便秘かもしれないと思ったら早めにご相談ください。
腹痛
お子様の腹痛の原因は様々ありますが、次のような症状には注意が必要です。速やかに小児科を受診してください。

- 顔色が悪い・ぐったりしている
- 波がない持続する腹痛
- 歩いたり咳やくしゃみをしたりするとお腹に響く腹痛
- 突然起こる激しい腹痛
- 痛みが強く、冷や汗をかくような腹痛
- 血便が出ている
- 呼吸の様子がおかしい
- お腹がパンパンに張っている
- 吐物が緑色
精巣捻転や卵巣茎捻転の場合も腹痛を訴えます。そういった場合も速やかに受診するようにしましょう。
頭痛

こどもでも頭痛は受診理由として多く、中には就学前のお子様が頭痛を訴えるケースもあります。頭痛は大きく一次性頭痛と二次性頭痛に分類される。一次性頭痛は片頭痛や緊張型頭痛など、二次性頭痛には脳腫瘍や頭蓋内出血などの器質的疾患が存在します。片頭痛や緊張型頭痛は頻度が多く、規則正しい生活(適度な運動・食事、適切な睡眠など)が治療の第一歩です。月に1度程度の頻度で、日常生活に支障がない程度の痛みであれば、自宅で様子をみても良いですが、頻度がそれ以上に増える、頭痛で学校を休む、寝込んでしまうなど日常生活に支障が出ている場合には、1度当院にご相談ください。
また、症状が進行している、頭痛が毎日のように生じている、嘔吐がある、多飲多尿がある、ふらついて手足が動かしにくい、物が二重に見えるなどといった場合は速やかに受診することをおすすめします。
食欲がないとき
 お子様に食欲がない時、考えられる原因は多くあります。
お子様に食欲がない時、考えられる原因は多くあります。
原因を特定する際には、いつから食欲がないのか、食欲がなくなる前後に何があったのかを考える必要があります。食欲がなくなると同時に元気もなくなっている、ぐったりしている場合は、早めに当院までご相談ください。
元気がないとき
お子様の様子が「何となくいつもと違う」と感じる場合(元気がない、機嫌が悪いなど)、それが病気に気が付くきっかけになることがあります。
特に生後3ヶ月頃までの乳児については、母乳やミルクを飲まない、顔色が悪い、元気がないなど、少しでも「何かおかしい」と感じたら、早めに受診するようにしましょう。
また、年齢に関係なく次のような症状が見られる場合も、早めに受診するようにしましょう。
- 呼びかけに対してあまり反応しない
- 目線が合わない
- ぐったりして起き上がらない
- 泣き声が弱々しい
- 顔や皮膚の色が悪い
- 苦しそうな呼吸
- 繰り返し嘔吐している
- 泣く、泣き止む、を周期的に繰り返している
- 重い腹痛や頭痛などがある